どうも、おりき( @oriki_ex18)です。
「哲学」と聞くと、なんだか難しそう…と、最初から読むのを諦めてしまう人は多いですよね。
でもね、それじゃもったいない!
哲学書は人の人生を豊にするための考え方がギュッと詰まっています。
 おりき
おりき
とはいえ、
初心者だと何から読めばいいのかわからないですよね。
そこで、哲学初心者のため、
- 初心者向け
- ベテラン向け
といった感じでカテゴリーを分けながら、おすすめの哲学の本を13冊紹介しています。
哲学の入門書、漫画で楽しく、みたいな本を集めているので、初心者でもサクサク読めると思います。
もちろん、ベテラン向けのマニアックな哲学書も用意しているので、ぜひ読んでみてくださいね。
また、記事内で紹介している一部の本は無料で読むことができます。
 おりき
おりき
なんてこともあるので、
どれを読めばいいか迷ったら、まずは無料の本を読んでみてくださいね。
この記事の目次
【初心者向け】おすすめの哲学の本
ソフィーの世界 哲学者からの不思議な手紙
「一番やさしい哲学の本」として記録的なロングセラー小説となり、映画化もされたノルウェー発の不思議な哲学ファンタジー。
主人公はごく普通の14歳の少女ソフィー。差出人不明の手紙を受け取った日から、彼女の周囲ではミステリアスな出来事が起こっていく。
ここがポイント!
哲学初心者でも小説として楽しめるのでおすすめです。
ソフィーが哲学を学びながら、そして、この手紙をくれるのは誰?と謎解きの要素を含めながら物語が進んでいくので、ワクワクしながら読み進めることができます。
小説として楽しんで読んでいるうちに哲学のことを学べるので、子供から大人までおすすめの一冊です
ムーミンの哲学
ムーミンと聞くと、かわいらしいキャラクターが思い浮かぶと思います。
しかし、ただかわいいだけではなく、それぞれのキャラクターはとても奥深い発言をたくさんしています。
その言葉から学ぶ哲学の本で、哲学という堅苦しいイメージがなく読みやすい本です。
ここがポイント!
堅苦しく、とっつきにくい「哲学」への拒否感がないです。
何気なくアニメを見た方が、そんな見方があるのかと思ったり、じっくり考えてみると深い内容であることに気付かされます。
ほのぼのストーリーかと思いきや、ムーミンパパやスナフキンの言葉には奥深さを感じます。
哲学用語図鑑
かわいいイラストと丁寧な解説で古代から現代までの各哲学者の思想や、用語の概要がわかりやすくまとめてあります。
哲学用語の説明を時代ごとに進めていき、その用語の対義語や具体例も載っています。
難しい言葉でも、イラストで喩えを表現しているので、視覚的にもイメージがしやすい一冊です。漫画のよう読み進められます。
ここがポイント!
哲学者の思想に興味があっても専門書を開くと言葉遣いが難しくて、読むのを諦めてしまいます。
この本は入門書として最良で、哲学に興味がある人を拒んだりはねつけたりはしません。
浅く広い知識ですがポイントを押さえていて、もっと学びたいという気持ちを持たせてくれます。
マンガ 老荘の思想
中国の思想家の荘子と老子の名言を読みやすい漫画にした本です。
「足るを知る」「朝三暮四」「上善は水の如し」など、道教の有名な言葉を取り上げています。
可愛いイラストと共に言葉の説明が書いてあるので読みやすいです。
ここがポイント!
この本では名言ごとに漫画が入っているので非常に読みやすいです。
天下を取ることやトップになるという思想が書かれた本とは違い、弱いことや無用なことなどについてを取り上げられていてます。
【ベテラン向け】おすすめの哲学の本
ツァラトゥストラかく語りき
ツアラツストラとはゾロアスター教の開祖であるゾロアスターのことを指します。
ツアラツストラ(ゾロアスター)の語りでは、従来の社会道徳に背を向けた「背徳」が展開されて、奨励されます。
旧来の社会の貴族的な偽善性を余すところなく明らかにしてくれるのが本書の内容です。
ここがポイント!
特筆すべきは語りのフォーマット。
原文のドイツ語で読むと味わい深いのですが、翻訳された日本語でもフィクションめいた哲学風の特異な文体は、おすすめポイントです。
スタイルでは新約聖書、プラトンの対話篇、ソクラテス以前の哲学作品に言い回しが似ていて、しばしば自然現象をレトリックや説明の手段に使うことがある点が魅力です。
嫌われる勇気
対人関係の悩み、人生の悩みを100パーセント消し去る本です。
アドラーは人間の悩みは、全て対人関係の悩みであると断言しており、対人関係を改善していくための具体的な方策を提示してくれる本となっております。
ここがポイント!
生きていれば誰でも一度は悩んだことがあると思います。
社会人であれば職場の人間関係、学生であればクラスメートや友人などの関係。
人から嫌われたい方はいないと思いますが、この本を読むと人に嫌われても良いことを学べます。
人に合わせて自分の意見が言えない人、嫌われるのが嫌でやりたいことができない人、この本を読むと考え方が変わり気持ちがスッキリするはずです。
出家とその弟子
浄土真宗の開祖である親鸞とその弟子たちの物語です。
親鸞は悪人こそ極楽浄土に行くことができるとといた僧として有名ですが、彼自身にも弱さがあり、迷いがありました。
その弱さや迷いを克服していく姿が弟子たちとのかかわりの中で描かれています。
ここがポイント!
人が生きていくうえで避けることができない「死」「罪」「赦し」などについて物語形式でわかりやすく説いています。
仏教とキリスト教との接点も書かれています。
この本の最大の魅力は、罪あるものとして生まれた人間がいかにして救われるかという大きな問題に対して、ヒントを与えてくれるところです。
親鸞は、罪を自覚した者こそが救いを求め、すがる心を持つところに解決を求めていますが、救いに至る過程が書かれている点がおすすめです。
これからの「正義」の話をしよう
ハーバード大学の人気講師マイケル・サンデル先生のJUSTICEの講義を主にした哲学書です。
あなたは列車の運転手で線路を走っています。
目の前に5人の人がいて、このままだと列車で轢いてしまいます。
路線を変更するレバーを引くと5人は轢かずに済みますが、また別の1人が引かれてしまいます。
あなたはレバーを轢きますか?どちらが正義ですか?
このような問いが本書では書かれています。
ここがポイント!
講義の中には、本当に起きた裁判の例などがあります。
自分が裁判官だったらどんな考えで読み解くだろうか、自分が加害者だったら、被害者の親族だったら、など色んな目線で読むことができます。
死に至る病 あなたを蝕む愛着障害の脅威
人間にとってに恐れるべきものとは何か、生きていく上ですがるべきものとは何かを示しています。
自己の中にある概念が思いのほか暗く、深いものであるが故の不安定な精神がもたらす「怖さ」の様なものを切々と説かれています。
ここがポイント!
単にポジティブな精神論ではないところがおすすめポイント。
「これ以上、どう苦しめばいいんだ」という状況に陥った時に、その状態を分析して冷静にさせられ、前を向くきっかけになります。
自己を救済させる為には、ある程度客観視した概念が必要であるという事なのかもしれないと、気付かせてもらえる一冊です。
生きていくあなたへ 105歳 どうしても遺したかった言葉
105歳で亡くなられた日野原さんの言葉を集めた本です。
生涯現役の医師として活躍された日野原さんが大切にされていた言葉がたくさん記されていて、どう生きていくべきかについて深く考えさせてくれます。
「死が命の終わりではない」など、心に残る言葉が多く記されています。
ここがポイント!
この本は「どう生きるべきか」を考えている人におすすめの本です。
「死」が人生の終わりではないこと、愛するとはどんなことか、人をゆるすことがどんなに難しいことか、大切なことはすぐにはわからないなど、
人生について考えている人が参考になることばかりです。
命の大切さを知ることができる一冊です。
ニーチェの言葉
ニーチェの今まで出した本の名言集です。
厳しいものもあれば気持ちが楽になるような言葉があったり、まったく新しい斬新な考えの名言なども載っています。
ここがポイント!
人生において何が大切であるかが書いてあり、何かに執着したり、人間ならではの恨み辛みなどの難しい問題も無神論者ならではの視点での名言がとてもためになります。
名言集なので長ったらしい難しい本ではないので読みやすいです。
落ち込んだときや何かに悩んだ時に読むと勇気づけられる一冊です。
10代からの哲学図鑑
哲学と認識論、形而上学、心の哲学、論理学、倫理学と政治哲学の5章からなります。
難解な哲学用語の理解で最初からつまづくことが無いように、わかりやすい文章と図解により哲学についての理解を深めていくことができる内容となっています。
ここがポイント!
「10代からの」「図鑑」と本のタイトルにあるように、哲学に対する仕切りが下がるところ。
難しい言葉の理解で嫌になってしまうことが無いように、わかりやすい言葉や図が使われています。
純粋理性批判
『純粋理性批判』という哲学書は、人間の理性の能力の及ぶ範囲を、その理性そのものが検討して批判をするという内容です。
哲学者カントの言い回しを借りれば、形而上の学である哲学に先行して理性そのものが適用される範囲を限界づける、いわば哲学するという行為の予備門ということになります。
「認識」の作用である理性そのものは、理性から認識される範囲の外にあることを明らかにした哲学書です。
本書を指して認識論の「コペルニクス的展開」と評することがあります。
ここがポイント!
哲学の伝統を形成する認識論のうちで懐疑論は、理性の認識作用が人間の精神がもたらすものだとしています。
懐疑論は、このように問いかけることによって認識そのものが成立するか否かをも問題としています。
カントは、認識が実在しないとする従来の懐疑論に対して、人間の経験の基礎を成す認識作用は、すべての人間にとって妥当なものであることを主張しました。
旧来の懐疑論を打破して、人間認識の新たな可能性を確立したことがわかる一冊です。
 おりき
おりき
夢解釈
無意識の心理学である精神分析学を創始したジグムンド・フロイトが1900年に発表した書が『夢判断』です。
この本は心理学書でありますが、哲学にも大きな影響を与えたので哲学書として論じます。
夢については古来から研究が行われてきましたが、神学的な説明に終始していました。
その後、睡眠中に感覚を刺激すると夢にその刺激が反映されることが明らかになり、さらにフロイトは感覚的刺激だけでなく、夢の内容に精神の状態を紐づける議論を展開しました。
ここがポイント!
無意識の心理構造を解き明かした点でこの哲学書をお薦めします。
フロイトの唱えるところでは、夢の素材は記憶に由来しており、どの素材が選ばれるかは意識的ではない(無意識)のです。
乱雑に思える夢の内容は無意識の心理的な過程に基づいた統合性を保っていて、夢の雑多なできごとも1つの物語として完結させられています。
読書をするならオーディオブックがおすすめ
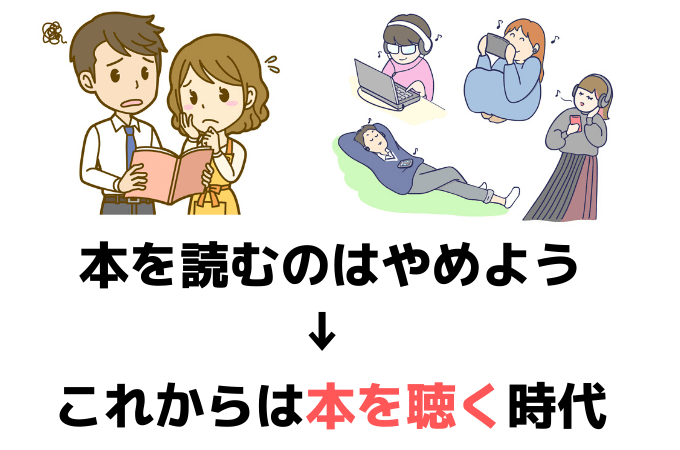
読書をするなら『オーディブル』がおすすめです。
目で読む読書とは違い、耳で聴く読書なので
- 運転中
- 通勤・通学
など、いつでもどこでも読書をすることができます。
もし、通勤に1時間かけている人がオーディブルを利用すると
- 1日で1時間
- 1ヵ月で30時間
- 1年で365時間
も通勤しながら読書ができます。
1冊5時間かかる本だとしたら
1ヵ月で6冊分の知識をインプットできるということ。
 おりき
おりき
これまで
「この時間無駄だな・・・」
と思っていた時間が自己投資の時間になります。
今ならオーディブルを30日間無料で体験することができます。
興味のある人はお試し感覚で利用してみてください。
【5分でわかる!】オーディブルを使った感想|評判や口コミ、おすすめ本を紹介!
 【5分で超わかる!】オーディブル歴3年の感想|評判や口コミ、おすすめ本を紹介!
【5分で超わかる!】オーディブル歴3年の感想|評判や口コミ、おすすめ本を紹介!
まとめ
さて、ここまで「おすすめの哲学の本」を紹介してきました。
哲学書を読むことで人生がドカンッと変わるとは思いません。
ただ、何かのきっかけで哲学書の言葉が自分を救ってくれる…なんてこともあります。
もし、この記事で気になる本を見つけたら、ぜひ読んでみてください。
これからも、おすすめの哲学の本が見つかり次第、随時追加していくのでチェックしてくださいな。
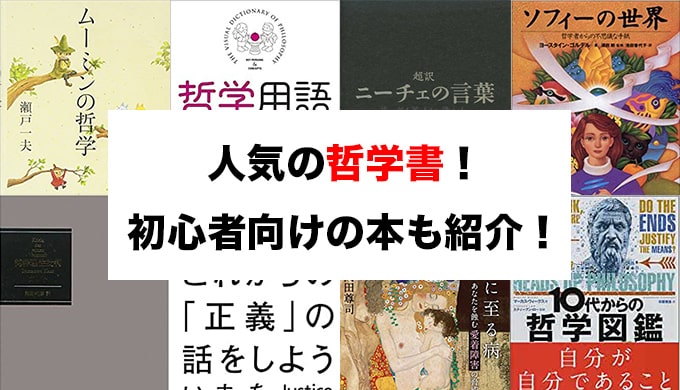

























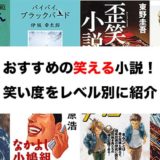
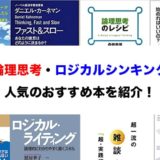
コメントを残す