どうも、おりき( @oriki_ex18)です。
「社会人なのに歴史がわからない人は教養がない」
こんな風に言われることがありますし、僕自身確かにそうかも…と思います。
とはいえ、
 おりき
おりき
・歴史ってゴチャゴチャして苦手
・世界史ってどこから覚えればいいのかわからない
という人も多いかと思います。
そこでこの記事では、歴史・世界史が苦手、嫌いという人でも「歴史・世界史が楽しくなる本」を紹介していきます。
この記事を書くためクラウドソーシングで『歴史・世界史オタク』に協力してもらいました。
ですので、ここでおすすめする本は、歴史・世界史オタクが選んだ最高の一冊ということです。
カテゴリー分けとして、
- 小学生向け
- 中学生向け
- 高校生向け
- 社会人向け
と区別していますが、誰にとってもおすすめできる本を揃えています。
日本、中国、ヨーロッパなど、たくさんの国の歴史本をまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
こんな人におすすめの記事
- 学校の勉強以外に知識を身につけたい
- 社会人になってから歴史に興味がでた
- いろんな歴史・世界史の分野を知りたい
この記事の目次
【小学生向け】おすすめ歴史の本
日本の歴史
こんな内容
石器時代から現代までの歴史が24冊にまとめられており、歴史をまんがで読むことで学ぶことができるようになっています。
まんがの絵も親しみがあり時代それぞれのエピソードを交えた物語形式の作品です。
ここがポイント!
私が小学生のころ図書室で良く読んでおり、あまりに面白く借りていたほどです。
歴史を好きになった理由はこの漫画の読みやすさと説得力のある物語の構成にあり、歴史を学び始めた小学生は一読する事をおすすめします。
歴史に興味、関心を持つきっかけになると思います。
また、イラストに親しみがあり歴史上の人物を覚えやすいと思います。
ドラえもんの社会科おもしろ攻略 日本の歴史
こんな内容
登場人物の時代背景や内容がわかりやすく読みやすいです。
文章が短くわかりやすい解説付きなので、小学校低学年からでも飽きずに読み切ることができます。
ここがポイント!
大まかな歴史の内容がわかるので、歴史がすきになってほしいと願う保護者にはおすすめです。
こどもが好きなドラえもんの歴史マンガなので、気に入ってくれること間違いないしです。
【中学生向け】おすすめ歴史の本
のぼうの城
こんな内容
日本の戦国時代、豊臣秀吉が天下統一に向け、北条家を攻めました。
結果的に北条家は負けてしまい、北条家の小田原城の他、数々の支城が落城するのですが、唯一落城しなかった忍城の話です。
豊臣秀吉の腹心、石田光成が大将の約2万人の豊臣軍に対し、わずか500人の忍城が三成に「よき戦いであった」といわしめる戦いぶりを見せます。
その強さの秘訣は武力ではなく、忍城の領民と士族たちの関係性が作用しています。
読後が爽快な小説です。
ここがポイント!
豊臣秀吉とその腹心の関係性、その時代の各地の大名の力関係などが読み取れ、石田光成など細かな描写があり歴史の教科書ではわからない人間味が見えます。
また戦国時代の領民の感覚がわかりやすく描かれており、田植えの踊りなど大衆の娯楽で敵味方がなくなるなど、戦国時代の戦の在り方も見えます。
石田光成が水攻めの際に施した堤防の跡が現在もあり、随所の現在ではどの地域にあるかという説明もあり、理解も深まりやすいです。
アンの娘リラ
こんな内容
カナダの有名な小説『赤毛のアン』のシリーズの1つです。
アンの末娘リラが主人公です。
人生で最も華やぐ10代の青春時代に第一次世界大戦が勃発し、兄弟・友人・恋人が次々と出征するのを見送り、不安と緊張の中、一人前の女性としてたくましく成長する姿が描かれています。
ここがポイント!
フィクションですが、第一次世界大戦下のカナダの様子が詳細に綴られています。
主人公が出征した男たちから受け取る手紙によって、実際の戦地や不潔で、死と隣り合わせの塹壕の様子が詳細に分かります。
一番のポイントは主人公が女性であることです。
歴史の本で特に戦争を扱う場合、男性目線で戦地の様子を語られるものが多いです。
その点、『アンの娘リラ』は男たちを戦地に送り出した後の村の様子や留守を守る女たちの心理が作中のリラの日記によって細かく記されています。
作者が牧師の妻だったという点から、この時代のキリスト教会の様子や信者たちの宗教観にも触れられているので、戦時下の宗教のあり方が描かれており、その点も興味深く面白いです。
【高校生向け】おすすめ歴史の本
チェーザレ
こんな内容
中世ヨーロッパの歴史がとても入ってきやすい漫画シリーズです。
主人公はチェーザレでイタリア、フランスの歴史的背景が忠実に描かれています。
戦のシーンが多いですが個々の人物が美しく描かれていてついつい次巻をよんでしまう面白い作品です。
ここがポイント!
世界史は単語等を断片的に覚えても流れや時代背景が日本史以上に捉えにくいです。
しかし、この漫画をずっと読んでいるとヨーロッパ全体をみながら個々の国を理解できるのでとても役に立ちます。
実際に高校の世界史の先生に紹介されたものなので、ただの漫画本ではなく中身が濃い良質な学習漫画だと思います。
学生さんはもちろん大人の方も楽しく教養を身につけられると思います。
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書
こんな内容
覚えるのがめんどくさいヨーロッパ史~現代までを数珠つなぎで1つのストーリーにした一冊。
また地図や図解をもちいた解説が豊富で世界史の流れや、人名がおどろくほどに覚えやすいので知識ゼロでも楽しく読める。
ここがポイント!
ほかの世界史本と違い年号が一切でてこず、すべての出来事を「因果関係」で数珠つなぎに解説しています。
そのため世界史のストーリーが際立ち、世界史の理解が驚くほど深めることができます。
また、年号もあわせて覚えたい人向けに、巻末付録に主要な出来事を中心にした年表も掲載しているので便利です。
三国志
こんな内容
後漢の末期の混乱期から、魏・呉・蜀の三国鼎立時代の歴史を基にした小説。
関羽・張飛・趙雲などの豪傑や諸葛孔明や司馬仲達の軍師が多数登場して、その武力や知力に魅了される作品で同時に後漢から三国,晋の時代の歴史が分かるます。
ここがポイント!
中国の地図を片手に読んでいくといつの間にか中国の地理が頭に入ってしまいます。
同時に魏・呉・蜀の三国を建国した曹操・孫権・劉備の各人の個性的なキャラクターが非常に個性的です。
その下につかえる部下たちのも主人に合ったキャラクターで、各国ごとの君臣の関係を比較しながら見ていくと非常に興味深く読める小説です。
源氏物語の時代(一条天皇と后たちのものがたり)
こんな内容
源氏物語が書かれた時代である一条天皇の治世の解説本です。
また、その当時の人々、皇族、公卿、女房達の残した日記や作品から後世「聖代」と讃えられた一条朝の姿を浮き彫りにしていきます。
そして紫式部が描いた「物語」が「現実の歴史」を鏡合わせの螺旋構造の様に取り込みながら描かれていたことが伝わってくる一冊です。
ここがポイント!
日本史の中でも名前が似ていてややこしい時代なので、各人物のキャラを頭で構築していくのに便利です。
(実資、公任、行成、一条、三条、後一条、後朱雀、後冷泉、後三条など)
これで読んでおけば各自の立ち位置迄確実に頭に入ってきます。
それと、源氏物語の大筋の話も把握できます。
マニアックな古文の設問として出てくる「小右記」(小野宮の右大臣日記)とか「権記」(行成の日記)など、
原文プラス現代語訳もあり、この少し前の時代の「大鏡」など盛りだくさんの正確な文献が出ているので、歴史と古文という一粒で二度美味しい本になっています。
銃・病原菌・鉄
こんな内容
人類史の要点を網羅的に紹介しながら、さまざまな考察を試みた本です。
生物としては同種であるはずのヒトが、征服する側とされる側とに分かれた多くの場面について、それぞれの立場が逆にならなかった背景を解説します。
タイトルの『銃・病原菌・鉄』は、本書の主なテーマを指している。
ここがポイント!
幅広い分野における発展や衰退を多角的に眺めることは、人類史を学ぶ上で大きな意味があると思います。
未知の環境がもたらすものと、その時に生き残った人々と命を落とした人々との差は、人類がコロナ禍で危機に直面している今こそ知っておきたいことです。
本書で具体的な新型コロナウイルス対策は得られませんが、誰も正解を知らない問題との向き合い方を考えるためのヒントとして、おすすめしたい本です。
十八史略
こんな内容
中国歴史書の中で『史記』、司馬遷、 『漢書』 班固 、『後漢書』 范曄 、『三国志』 陳寿など日本でもよく知られた中国の歴史書です。
「神話時代」から「南北宋」の時代まで正史としてブームを起こしています。
ここがポイント!
中国の子供向けの歴史読本で「三皇五帝」の伝説時代が面白いと思います。
世界各国に人類の起源がありますが、中国(東洋)らしい人間の起源があります。
人間の先祖は「蛆虫」であるというところに関心しました。
また、20世紀最大の歴史的発見、伝説の「殷」に記載があり中国史が300年遡ることになりました。
どこまでが伝説なのか中国史は面白い点が多くあります。
マゼラン 最初の世界一周航海
こんな内容
マゼランが世界を一周するときの経緯や航路、旅路の様子を日記にしたものが和訳されています。
歴史上の大航海時代に焦点をあてて書かれています。
後日談も書かれていて、この航海を成し遂げたあとのマゼラン艦隊の乗務員の末路まで知ることができます。
ここがポイント!
著者名を見ると「アントニオ・ピガフェッタ」という、マゼランの航海について行った人のものになっています。
航海中は、マゼランももちろん日記を書いていました。
なのになぜ、出版されたのがマゼランではなく、航海の同行人の日記なのでしょうか。
そんな謎もこの本には書いてあります。
科学が発展しきってない頃の航海がいかに大変だったのか、この航海を経て成果は今の何に生かされているのか。
この本を読めば世界の背景も見えると思います。
風雲児たち
こんな内容
物語は関ヶ原の戦いから始まり、徳川勢の勝利〜幕府成立以降の歴史エピソードが細かく描写されています。
愛蔵版コミックスで全20巻、現在も幕末編30巻以上が刊行中です。
ここがポイント!
まずは漫画という媒体なので読みやすいこと。
ギャグ漫画のテイストで重く暗いエピソードも重々しくなる寸前でギャグにして読み手としては暗い気持ちにならずに済みます。
おすすめなのは、細かいストーリーが重なって一本の物語に集約されていく様子を漫画を読み進めていくうちに実感できる事です。
これは長期連載ならではの醍醐味だと思います。
大人でも意外と知らない吉田松陰の「松蔭」がとある人物から取られた名前である事など、長く読み続けてこそ楽しめるエピソードが満載です。
「24のキーワード」でまるわかり!最速で身につく世界史
こんな内容
テレビプロデューサーが書いた「最速で身につく」ことを目的とした、バラエティに富んだテーマで構成される世界史解説書。
世界史を学ぶ前提として理解すべき歴史背景や考え方の説明に主軸が置かれており、それを様々なキーワードで、時系列で解説している。
ここがポイント!
テレビプロデューサーが作ったということもあり、限られた時間の中でいかにいかに面白く伝えていくかという視点が新鮮です。
キーワードも「戦争」「お金」「教養」と多岐に渡り、自身が興味のある部分から読んでも楽しく理解できる構成になっています。
受験生であれば苦手と感じるテーマから、ビジネスパーソンであれば仕事にかかわる分野から読み始めるとスムーズに理解が進み、その他の分野にも興味がわいてきます。
超約 ヨーロッパの歴史
こんな内容
ヨーロッパの歴史について書かれた本の翻訳です。
ページ数は300ページほどですが、ペーパーバックで全然重くなく、文章も平易で読みやすいです。
古代(ギリシア・ローマ)から中世、近代、現代のEUまでを扱っています。
ここがポイント!
高校生くらいまでは、日本の学生にとって、世界史、ヨーロッパの歴史との接点は、およそ教科書か、よくて日本の著者が書いたヨーロッパの歴史についての本だと思います。
ヨーロッパの文化の3つの要素と著者が言い切るものを知ることは、そういった日本の学生にとって、新鮮な経験になるはずです。
もともと大学の講義を本にしたものらしく、読みやすく書かれています。
マンガなどで読みやすくしたものはありますが、ただ読みやすいだけでなく、内容も読みごたえがあるものとして、一読の価値があると思います。
最後の将軍
こんな内容
徳川幕府15代将軍である徳川慶喜が時代にどう翻弄され、江戸幕府を畳もうと考えたのか、そしてその周囲でどのような動きがあったのかがこの1冊でわかる司馬遼太郎の傑作。
短時間で読むことができる江戸時代末期のストーリー。
ここがポイント!
日本の歴史の中でも260年も続いた政権はどこにもありません。
もちろん時代とともにその権力が浮き沈みし、最終的に自分の内で新しい時代につなごうと考えた徳川慶喜と言う人物がどのような心で時代を眺めていたのか。
今の日本もまさしく時代の節目です。
どのように新たな時代を迎えるべきか考える際の参考になると思います。
【社会人向け】おすすめ歴史の本
学校では教えてくれない日本史の授業
こんな内容
みんなが必修科目で歴史を習ったはずなのに、
「どうして源頼朝は天皇家を滅ぼさなかったの?」「どうして日本人は無謀と思われる戦争に反対できなかったの?」
と聞かれても、多くの人はうまく答えられません。
歴史年表の暗記では分からない、歴史上の出来事の本当の意味を長期的な視野で考え直す本です。
ここがポイント!
難しい歴史の専門用語を使わずに、新たな視点から歴史を解説しています。
一時代だけを切り取ってそこだけを評価するのではなく、歴史全体を通してその時行われたことが俯瞰的にとらえられます。
例えば、生類憐みの令は犬だけを守る失敗政策と思われがちですが、結果として「切り捨て御免」を減少させるなど、人が人を大切にする倫理観を養った政策としてわかります。
竜馬がゆく
こんな内容
大河ドラマにもなっているので、ある程度幕末の歴史が好きな人なら内容も知っていると思います。
混迷の幕末を駆け抜けた土佐藩の坂本龍馬が歴史に翻弄されながらも低い身分ながら大物を手玉に取って明治維新を成し遂げる様は痛快でここちよい。
ここがポイント!
基本的には実際の歴史に沿って物語は進行するのですが、作者の司馬遼太郎先生がよりストーリー性を深めるために脚色している部分も大きい。
タイトルからして「龍馬」ではなく「竜馬」となっているところからして意味をにおわせています。
彩を与えるために出てくる登場人物もみりょくてきで、かなりの長編小説ではありますが、一気に読んでしまうぐらいのおもしろさがあります。
経済で読み解く日本史
こんな内容
経済評論家の上念司さんが日本史を経済の視点から語った本です。
普通の歴史本のように、年表と人物を追っていくのではなく、お金の流れ、経済状況を中心に、
「だからこうなった」ということをわかりやすく、図やグラフといったファクトを元に解説しています。
ここがポイント!
子どもの頃に人物や年号を覚えさせられて、歴史が嫌いになった方も多いと思いますが、社会人になると歴史がわからない人は教養がないとみなされます。
だからといって、今から歴史を勉強し直すのはハードルが高いと思います。
しかし、この「経済で読み解く日本史」であれば、すらすら読めますし、今との比較も随所にちりばめられているので、読み終える頃にはしっかり頭に入っていることでしょう。
残酷な王と悲しみの王妃
こんな内容
全ての王や王妃がアニメの様な豪華でハッピーな生活を送っている訳ではないと教えてくれる本。
シリーズで計二冊あり、イギリスやスペイン、デンマーク等の王室が紹介されています。
ヨーロッパでは国を越えて輿入れするので、当時の世界情勢も学べます。
ここがポイント!
私自身は高校生の時に世界史は勉強しておらず、社会人になってから出会いました。
何も知らない状態でも本の内容は十分理解出来ました。
著者である中野京子さんは他にも数々絵画についての本も執筆されていて、この本でも各章の主人公にまつわる絵画が紹介されています。
歴史だけでなく絵画の教養も身に付くのがオススメです。
ローマ人の物語
こんな内容
ローマ帝国の歴史を、都市国家ローマが生まれた紀元前8世紀から順次記述しています。
なかでも、カルタゴとの戦争(ポエニ戦役)、カエサルシーザーによるガリア戦役などローマがいかに戦ったかを詳細に知ることができます。
会戦を得意としたローマの戦い方は手に汗を握るような書きぶりです。
ここがポイント!
「ローマは一日してならず」といわれます。
歴代の皇帝がどのように巨大な帝国を築き、維持していったかを知ることで現代にも通じる教訓を学ぶことができます。
また、「ポエニ戦役」として有名なカルタゴのハンニバルとローマのスキピオの戦いは興味深いです。
アウグストや五賢帝など高校の世界史で習ったのは表面的な学習ですが、この本を読むことでローマ人の戦い方・考え方や政治手法を知ることができます。
天璋院 篤姫
こんな内容
幕末に将軍の正室となった篤姫の物語です。
女性が主人公なので、女性で歴史が苦手な人におすすめです。
地方の姫にしかすぎなかった篤姫が、将軍の正室となり幕末の政争へ巻き込まれていく中での生き様が描かれています。
ここがポイント!
小説なので、歴史が苦手な人でも読みやすいです。
また、複雑な幕末の歴史が篤姫の視点からわかりやすく描かれています。
歴史上悪く描かれがちな篤姫を主人公とした事で「事実も色んな立場から見たら違う」ということや歴史を様々な立場からみる面白さを知ることができます。
幕府側、天皇側の視点を知ることで、複雑な幕末も興味を持ってみることができるのではないでしょうか。
「天下を狙った軍師」の実像
こんな内容
「稀代の軍師」とも呼ばれる武将の活躍の実態についてが書かれています。
私は軍師が好きなのでいろいろな軍師と呼ばれる本を読みましたが、大河のドラマも参考にしたような内容が書かれていると思います。
現在のビジネスにも通じるところがあると思います。
ここがポイント!
ピンチの時、新しい事業を始める時など、人生の節目を迎えるときが人には必ずあります。
自分が今後どうしたらよいのか考えるときに、参考にしていただき自分を磨き続けられればと思っています。
温故知新とはよくいった言葉で昔あったことは、形は違えど本質は今でも繰り返されています。
このようなことに気付いている人にはきっと参考になると思います。
日本国紀
こんな内容
日本の通史で日本史の全体像がわかります。
古代から平成までの歴史が14章にわけられ各時代ごとに書かれています。
神話の時代から万世一系の天皇を中心とした国家が2000年以上の歴史が続いている日本を作家百田尚樹が一本の線に繋いだ作品です。
ここがポイント!
歴史の授業は、部分的に切り取って行われることが多く、近代史に至っては授業でも取り上げられないことが多いです。
この作品は神話とされている時代から現代までを通して百田氏の言葉で語られており難しい言葉は使用されておらず、とても読みやすい作品です。
評論家には間違った解釈がされていると批判する動きもありますが、そもそも歴史はロマンなので自分たちのルーツを知るという意味ではこの作品が良いと思います。
山霧 毛利元就の妻
こんな内容
女性で日本の歴史小説家である永井路子さんが書かれた毛利元就と、鬼吉川と呼ばれていた吉川家から元就の妻となった美伊の方の夫婦の生涯の小説です。
三人の子供を産み、長男は後に毛利家の家督を継ぐ隆元、次男は吉川の実家を継いだ吉川元春、三男は小早川家の当主となる小早川隆景となり、毛利家は小国だった毛利家を大きくしていく夫婦とその息子たちの歴史小説です。
ここがポイント!
副題に毛利元就の妻とある様に、子供を産んでから、実家吉川家よりも毛利家の方が大事、自分は毛利家の人間になったという美伊の方の思いを感じられる小説です。
ボヤキ元就と言われていた様に、元就の若い頃は、周囲の大国に囲まれた小国の領主で周囲の顔を伺いながらうまく乗り切ることに必死でした。
その夫の元就を支えていた妻の凄さを感じる小説です。
この本が原作となり、NHKの大河ドラマでも放映された作品です。
乱と変の日本史
こんな内容
中世における日本史の転換点となった、もしくはその要因となった出来事を書き下ろした書籍。
出来事の背景、原因はもちろんのこと、そもそも何をもって乱と変を区別しているのか?といった疑問について詳しく記している。
ここがポイント!
日本史を語る上で欠かすことのできない、重要な戦い、争いを詳しく紐解き、勝者と敗者の違いやなぜ敗者とならざるをえなかったのか?といった本質をわかりやすく説明しています。
翔ぶが如く
こんな内容
明治維新で幕府を倒した薩摩藩の人たちが、維新後の政治の中で 武士の処遇を巡り、政府側に大久保利通らと激しく対立。
やがて薩摩に帰り士族の教育に力を入れていた西郷隆盛や薩摩藩を中心とした、不平士族との間で西南戦争が起きるまでを描いた小説です。
ここがポイント!
明治維新後の謎ともいえる西郷隆盛が起こした西南戦争。
維新で英雄として語り継がれる西郷隆盛や薩摩藩で新政府の要職に就いた薩摩の武士たちがなぜ政府に反乱を起こし、賊軍と呼ばれる道を選択してしまったのかを極めて詳細に記載しています。
なぜ敢えて薩摩藩の人たちが戦おうとしたかがこの小説を読むと理解できます。ぜひ読んでください。
歴史・世界史を効率よく学びたい人は要約アプリがおすすめ
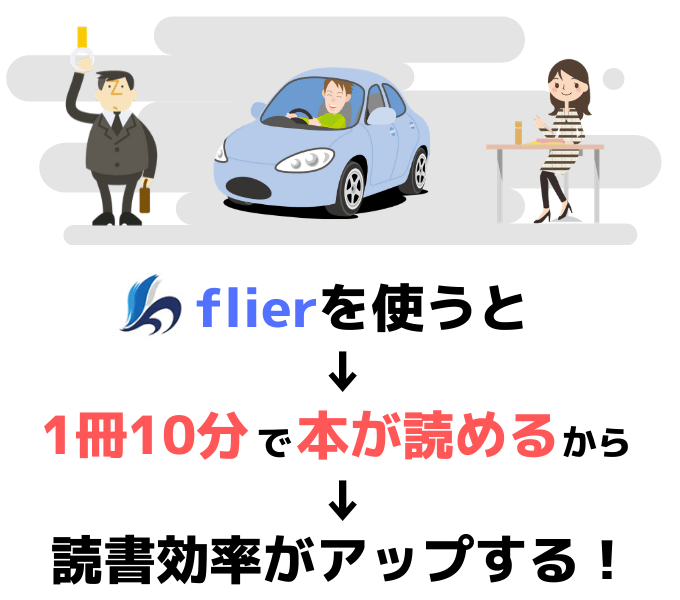
効率よく歴史・世界史を学びたいなら要約アプリ「flier」がおすすめです。
普通なら読むのに5〜6時間かかる本を、
専門家たちが大事な要点だけピックアップし、1冊10分程度で読めるようにまとめています。
- 通勤・通学
- 休憩時間
など、ほんの少しのスキマ時間を使って1冊分の読書ができるので効率よく知識をインプットできます。
歴史・世界史以外にも2,000冊以上の要約本が読めるので、興味のある方は利用してみてください。
本の要約アプリflier(フライヤー)を使った感想!評判や口コミ、料金を紹介!
 本の要約アプリflier(フライヤー)を使った感想!評判や口コミ、料金を紹介!
本の要約アプリflier(フライヤー)を使った感想!評判や口コミ、料金を紹介!
まとめ
- 歴史を学ぶことは、今を知ることである
- 歴史を学ぶのは、失敗を学ぶことである
つまり過去の歴史を学ぶことで、人生をより良くするためのヒントを知ることができる、ということ。
人生を…なんていうと大袈裟かもしれませんが、知見や視点を広げることは自分を成長させる一つの要因になります。
もしこの記事で気になった本があれば、まずは一冊、気軽に手にとって読んでみてくださいね!
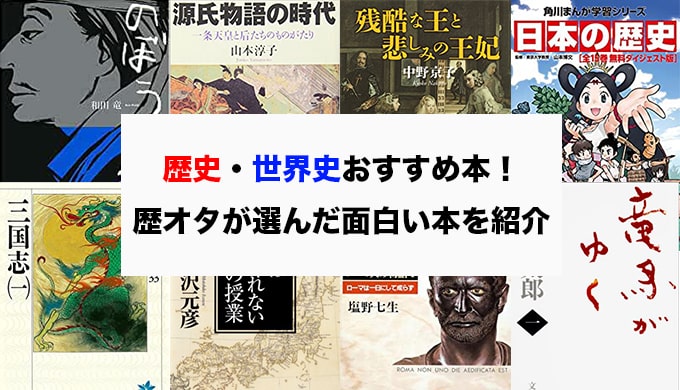










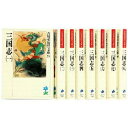



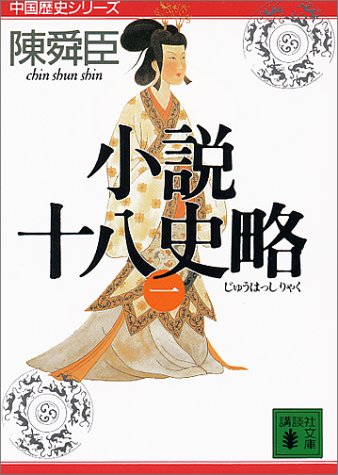



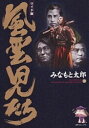



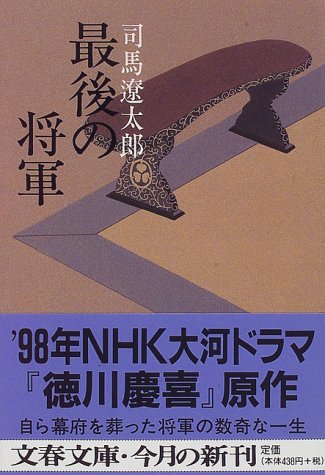




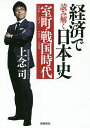













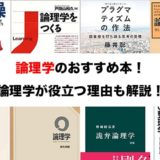
コメントを残す