この記事では、
効率よく本を読む9つの方法
を紹介します。
どうも、おりき( @oriki_ex18)です。
読書の効率ってなによ?
って思ってます?
「本なんて好きなように読めばいいんだよ」
というのが本音です。
しかし、僕たちの1日は24時間しかありません。
できるだけ少ない時間で
- 一文字でも多く
- 一行でも多く
- 一冊でも多く
読んで成長したいところです。
というわけで、
この記事では効率よく本を読む9つの方法について紹介します。
読書レベル1の初心者にピッタリな方法を用意したので、ぜひ試してみてくださいね。
この記事の目次
読書効率を上げる秘訣は1つ
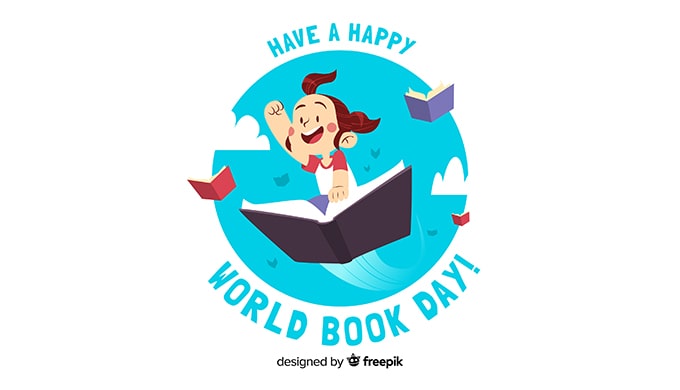
本の「全体像」を把握する
効率よく読書したいなら、
本の「全体像」を把握しながら読む
のが一番です。
- どんな人が書いた本なのか?
- この本は何を伝えたいのか?
- この本からどんな情報がわかるのか?
といったことですね。
この全体像がぼやけてると、頭に入ってこないし、印象にも残りません。
当然、速く読むことだってできません。
とくに、読書が苦手な人は、全体像を意識して読むだけで、
- 理解度
- 読む速さ
が格段にアップします。
次の項目では、
全体像を把握する
をテーマにしながら、読書効率がアップする9つの方法を紹介します。
読書効率をアップさせる9つの方法
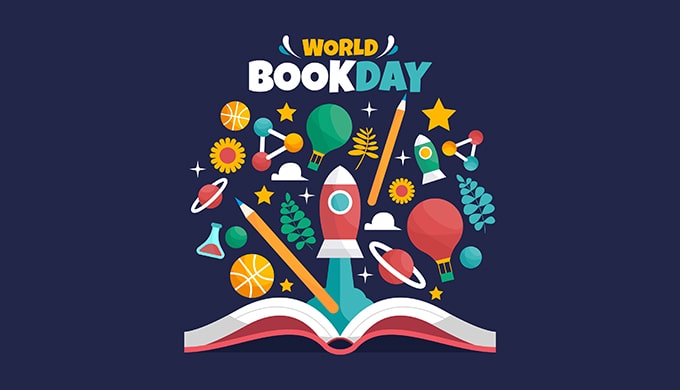
どれも簡単なので、参考にしてみてくださいね。
本の帯を読む
本の帯には、
その本の重要なポイントが書かれています。
例えば、この本だと、
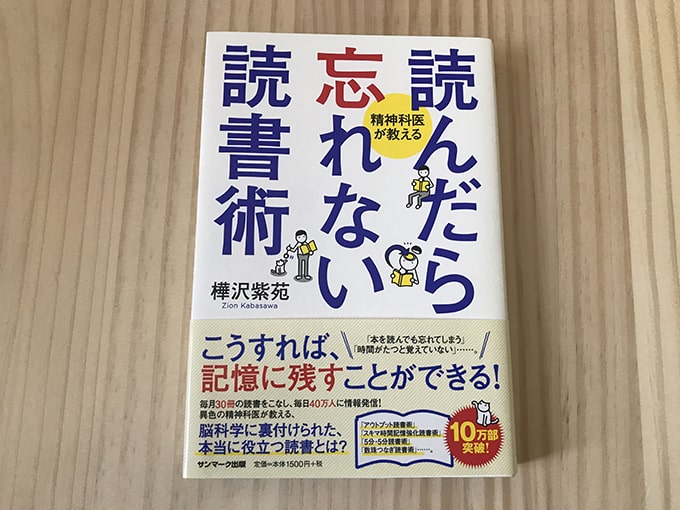
毎月30冊の読書をこなし、毎月40万人に情報発信異色の精神科医が教える、脳科学に裏付けられた、本当に役立つ読書とは?
(引用:読んだら忘れない読書術)
と書いてあります。
帯からわかることは、
毎月30冊読書してる精神科医が、脳科学をもとに”忘れない読書術”を教えてくれる
です。
帯を読むだけで、本の全体像が分かりますよね。
これを
- 知ってる
- 知らない
では、読む速さも理解度も大きく変わります。
著者について調べる
本を読む前に、著者について調べるのもおすすめです。
- 性別は?
- 年齢は?
- 経歴は?
- 普段どんな仕事してる?
などです。
どんな人物が書いた本なのか知るだけで、理解度は変わります。
著者が
- ツイッター
- フェイスブック
- インスタグラム
をやってるなら、そちらをチェックするのもおすすめです。
というダイエット本を書いてる著者が、100kgオーバーの女性だったら、
 おりき
おりき
って思いますよね。
この育毛剤を使うと、10代の頃のようにフサフサになりますよ!
と育毛剤をおすすめしてる人の頭が、ツルツルだったら、
 おりき
おりき
嘘つけー!
このハゲー!
って言いたくなります。
つまり、
どんな人物に言われている言葉なのかを理解しておくだけで、説得力や納得感が変わります。
要約アプリを使う
本の要約アプリ『flier(フライヤー)』を使うと、読書効率がグッと上がります。
僕の場合だと、
- 気になる本を見つける
- flierで要約を読む
- 面白そうなら本を買う
- 本を読む
という感じで、本を購入する判断材料としてflierを使っています。
 おりき
おりき
他にも、
- ハズレ本を買うリスクが減る
- 無駄なお金を使わなくて済む
こんなメリットがあります。
要約本を読んだことにより、記憶の下地(内容を理解)ができてるので、
 おりき
おりき
という心配も減ります。
読んだ内容をすぐ忘れるって人は、おすすめなので使ってみてください。
flierを使った感想を書いた記事を用意しているので、気になる人は参考にしてみてくださいね。
本の要約アプリflier(フライヤー)を使った感想!評判や口コミ、料金を紹介!
 本の要約アプリflier(フライヤー)を使った感想!評判や口コミ、料金を紹介!
本の要約アプリflier(フライヤー)を使った感想!評判や口コミ、料金を紹介!
「マンガでわかる」を読む
知識のない分野を学ぶなら、
「マンガでわかる」は最高の入門書
です。
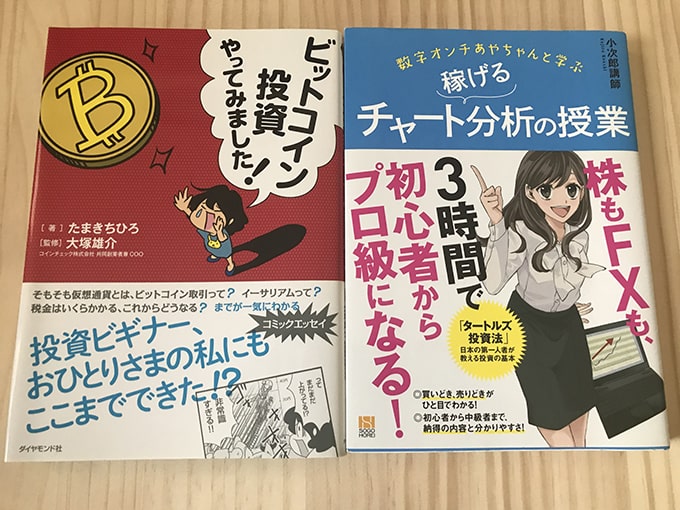
 おりき
おりき
「マンガなんか読んでんのかよ〜」
「ぷぷぷ〜」
って、バカにしながらマウント取ってくる人たちがいますが、気にしなくて大丈夫です。
マンガだから内容が薄いかというと、そんなことはないし、
専門家が重要なポイントだけをギュッと詰めこんで、構成しているので分かりやすいです。
むしろ、サクッと知識を得たいときは、マンガ版を読むのがおすすめです。
あらすじを読む
本のはじめに書かれる『あらすじ』は必ず読みましょう。
基本的に、あらすじには、
その本で著者は何を伝えたいのか?
について書かれています。
- どんな人のために書いたのか?
- なぜ、この本を書こうと思ったのか?
- この本を読むと、どんな情報が得られるのか?
などです。
あらすじ部分を読むと、その本の全体像がハッキリするので、読み飛ばしは厳禁ですよ。
目次を読む
目次を読まない人は多いですが、必ず読みましょう。
各章の見出しを読むだけで、
- どんなことが書いてあるのか?
- 何がわかるのか?
を把握できます。
とはいえ、
目次をバーッと読んでも、本文を読んでる最中に目次の内容なんて忘れてしまいます。
なので、おすすめは、
各章ごとに目次を見直す
という読み方です。
- 1章の目次だけ読む
- 1章を読む
- 2章の目次だけ読む
- 2章を読む
こんな感じ。
「1章では、こんなことがわかるのかな〜?」
くらいの理解度でOKです。
簡単に内容を把握しておくと、スイスイ読み進めることができて、記憶もしやすくなります。
つまらない本は読むのをやめる
読んでいてつまらない本は、読まないほうがいいです。
つまらんなー。と思って読んだ本の知識が役に立つことはありませんし、
そもそも、つまらない本の内容はすぐ忘れます。
- 時間の無駄
- 効率が悪い
- 読む意味がない
ってことです。
お金を出して買ってるので、
「せっかく買ったから読まないと・・・」
って思う気持ちも分かります。
でも、そこはグッと堪えましょう。
次読む一冊が最高の本だと信じて、そっと閉じましょう。
スマホでメモをとる
スマホでメモをとりながらの読書は超おすすめです。
ある程度、サクサク読んでいると内容を忘れてしまうことってありますよね。
書くメモと違って、スマホなら
- 手間がかからない
- メモが汚くならない
- いつでも読み返せる
などのメリットがあります。
 おりき
おりき
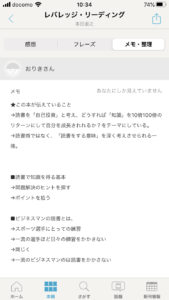
読書効率で悩んでいる人に多いのが、
じっくり読んで本の内容を100%覚えようとする
タイプです。
ただ、基本的に本の内容を100%覚えられる人はいません。
一生懸命覚えようとするのは、時間がかかって効率が悪くなります。
なので、
10%記憶できれば良い
くらいの気持ちで、大切なポイントをメモしながら、読み進めたほうが効率的です。
もっと言うと、
メモしたポイントは、自分にとって価値ある情報です。
スマホメモを継続すると『価値あるメモ』がどんどん溜まっていく、というメリットにもなります。
音声読書をする
本を耳で聴く『音声読書』もおすすめです。
人間は、
見る(視覚)より、
聴いた(聴覚)ほうが、
記憶しやすいということがわかっています。
例えば、
- テレビCMで流れる音楽を覚えている
- 友達が歌ってた曲を覚えてる
などの経験ってありませんか?
あれがまさに、聴いたほうが記憶しやすい証拠です。
僕の場合、
- 通勤時:音声読書
- その他:普通の読書
といった感じで、状況に応じて読書の方法を変えています。
歩いてるときでも、
電車に乗ってるときでも、
読書時間になるので、かなり効率的かなと思います。
 おりき
おりき
まとめ
この記事では、読書効率をアップさせる方法について紹介してきました。
まとめると、
本の「全体像」を把握し、スマホでメモしながらサクサク読みましょう!
という感じです。
ちなみに、僕が読書するときは、
- 著者について調べる
- 要約アプリを使う
- あらすじを読む
- 目次を読む
- メモをとる
この5つは必ず行っています。
1つでも良いのでマネしてみてくださいね。
こちらの記事もどうぞ
本を読むのが遅い…と悩んでいる人は、下記の記事を読んでみてください。
読書のスピードをあげるコツについて解説しています。
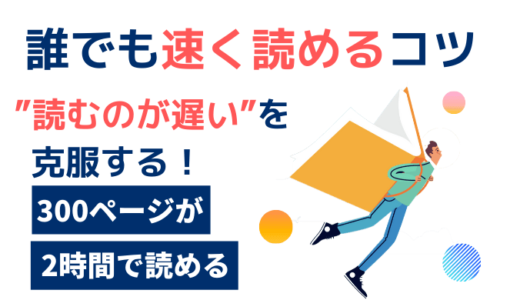 【1冊2時間で読める】読書するのが遅いを克服|誰でも速く読める2つのコツ!
【1冊2時間で読める】読書するのが遅いを克服|誰でも速く読める2つのコツ!
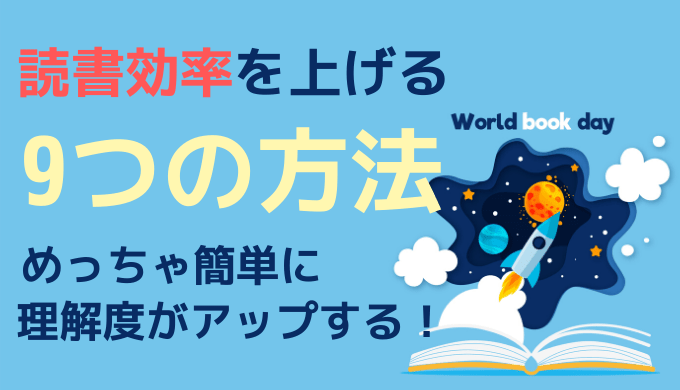
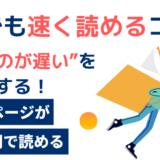
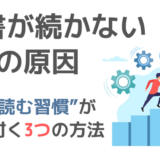
コメントを残す